大阪府の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
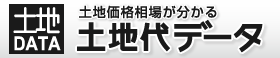
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
| 順位 | 市区町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪市 | 107万6586円/m2 | 355万8962円/坪 | +7.57% |  |
| 大阪市北区 | 383万7250円/m2 | 1268万5123円/坪 | +11.39% |  | |
| 大阪市中央区 | 372万1411円/m2 | 1230万2187円/坪 | +12.73% |  | |
| 大阪市西区 | 152万3636円/m2 | 503万6814円/坪 | +17.02% |  | |
| 大阪市阿倍野区 | 92万4000円/m2 | 305万4545円/坪 | +7.21% |  | |
| 大阪市浪速区 | 86万5625円/m2 | 286万1570円/坪 | +12.57% |  | |
| 大阪市福島区 | 86万4714円/m2 | 285万8559円/坪 | +11.79% |  | |
| 大阪市天王寺区 | 84万8250円/m2 | 280万4132円/坪 | +6.78% |  | |
| 大阪市淀川区 | 69万2555円/m2 | 228万9439円/坪 | +7.58% |  | |
| 大阪市都島区 | 40万0600円/m2 | 132万4297円/坪 | +5.44% |  | |
| 大阪市東成区 | 32万1500円/m2 | 106万2809円/坪 | +7.43% |  | |
| 大阪市住吉区 | 30万3200円/m2 | 100万2314円/坪 | +3.72% |  | |
| 大阪市城東区 | 30万2000円/m2 | 99万8347円/坪 | +6.99% |  | |
| 大阪市港区 | 28万2125円/m2 | 93万2644円/坪 | +4.90% |  | |
| 大阪市鶴見区 | 26万2400円/m2 | 86万7438円/坪 | +6.83% |  | |
| 大阪市旭区 | 26万1333円/m2 | 86万3911円/坪 | +4.41% |  | |
| 大阪市東淀川区 | 25万2714円/m2 | 83万5419円/坪 | +5.90% |  | |
| 大阪市東住吉区 | 25万0857円/m2 | 82万9279円/坪 | +2.45% |  | |
| 大阪市住之江区 | 23万0166円/m2 | 76万0881円/坪 | +5.34% |  | |
| 大阪市大正区 | 21万3000円/m2 | 70万4132円/坪 | +2.07% |  | |
| 大阪市西淀川区 | 20万7500円/m2 | 68万5950円/坪 | +2.78% |  | |
| 大阪市生野区 | 20万0285円/m2 | 66万2101円/坪 | +2.53% |  | |
| 大阪市平野区 | 19万9777円/m2 | 66万0422円/坪 | +2.32% |  | |
| 大阪市此花区 | 19万4600円/m2 | 64万3305円/坪 | +3.67% |  | |
| 大阪市西成区 | 19万3800円/m2 | 64万0661円/坪 | +5.25% |  | |
| 2位 | 吹田市 | 31万4560円/m2 | 103万9867円/坪 | +4.37% |  |
| 3位 | 豊中市 | 25万3192円/m2 | 83万6999円/坪 | +4.00% |  |
| 4位 | 茨木市 | 25万2904円/m2 | 83万6048円/坪 | +3.24% |  |
| 5位 | 箕面市 | 24万3820円/m2 | 80万6016円/坪 | +2.90% |  |
| 6位 | 池田市 | 22万5300円/m2 | 74万4793円/坪 | +1.31% |  |
| 7位 | 守口市 | 22万2125円/m2 | 73万4297円/坪 | +5.72% |  |
| 8位 | 高槻市 | 21万1826円/m2 | 70万0254円/坪 | +2.40% |  |
| 9位 | 東大阪市 | 17万3628円/m2 | 57万3977円/坪 | +0.64% |  |
| 10位 | 藤井寺市 | 16万6933円/m2 | 55万1845円/坪 | +1.35% |  |
| 11位 | 摂津市 | 16万2200円/m2 | 53万6198円/坪 | +1.33% |  |
| 12位 | 堺市 | 16万1472円/m2 | 53万3792円/坪 | +2.70% |  |
| 堺市北区 | 21万6545円/m2 | 71万5852円/坪 | +3.16% |  | |
| 堺市堺区 | 20万7666円/m2 | 68万6501円/坪 | +2.37% |  | |
| 堺市東区 | 15万6333円/m2 | 51万6804円/坪 | +3.26% |  | |
| 堺市西区 | 15万1050円/m2 | 49万9338円/坪 | +3.93% |  | |
| 堺市中区 | 11万0670円/m2 | 36万5851円/坪 | +2.05% |  | |
| 堺市南区 | 9万8133円/m2 | 32万4407円/坪 | +0.66% |  | |
| 堺市美原区 | 7万2200円/m2 | 23万8677円/坪 | +1.41% |  | |
| 13位 | 寝屋川市 | 15万5266円/m2 | 51万3278円/坪 | +3.34% |  |
| 14位 | 枚方市 | 15万3859円/m2 | 50万8625円/坪 | +2.88% |  |
| 15位 | 四條畷市 | 15万2250円/m2 | 50万3305円/坪 | +3.34% |  |
| 16位 | 大東市 | 14万9275円/m2 | 49万3471円/坪 | +2.83% |  |
| 17位 | 門真市 | 14万6500円/m2 | 48万4297円/坪 | +5.70% |  |
| 18位 | 八尾市 | 14万1806円/m2 | 46万8780円/坪 | +1.21% |  |
| 19位 | 高石市 | 13万4900円/m2 | 44万5950円/坪 | +4.12% |  |
| 20位 | 島本町 | 13万3666円/m2 | 44万1873円/坪 | +1.49% |  |
| 21位 | 交野市 | 13万1671円/m2 | 43万5277円/坪 | +1.98% |  |
| 22位 | 柏原市 | 12万7140円/m2 | 42万0297円/坪 | +0.88% |  |
| 23位 | 松原市 | 12万5250円/m2 | 41万4049円/坪 | +1.28% |  |
| 24位 | 泉大津市 | 11万9333円/m2 | 39万4490円/坪 | +1.61% |  |
| 25位 | 大阪狭山市 | 10万4750円/m2 | 34万6280円/坪 | +1.52% |  |
| 26位 | 羽曳野市 | 10万2400円/m2 | 33万8512円/坪 | +0.03% |  |
| 27位 | 岸和田市 | 9万3566円/m2 | 30万9311円/坪 | +0.89% |  |
| 28位 | 泉佐野市 | 8万8180円/m2 | 29万1504円/坪 | +1.75% |  |
| 29位 | 和泉市 | 8万3266円/m2 | 27万5261円/坪 | +0.90% |  |
| 30位 | 忠岡町 | 8万2933円/m2 | 27万4159円/坪 | +1.31% |  |
| 31位 | 富田林市 | 7万9327円/m2 | 26万2238円/坪 | +0.90% |  |
| 32位 | 河内長野市 | 7万5992円/m2 | 25万1214円/坪 | +0.44% |  |
| 33位 | 貝塚市 | 6万8070円/m2 | 22万5024円/坪 | +0.37% |  |
| 34位 | 熊取町 | 5万9680円/m2 | 19万7289円/坪 | -1.17% |  |
| 35位 | 田尻町 | 5万3750円/m2 | 17万7685円/坪 | +0.23% |  |
| 36位 | 太子町 | 5万2400円/m2 | 17万3223円/坪 | -0.15% |  |
| 37位 | 阪南市 | 4万5444円/m2 | 15万0229円/坪 | -0.64% |  |
| 38位 | 泉南市 | 4万4855円/m2 | 14万8282円/坪 | -1.33% |  |
| 39位 | 豊能町 | 3万3833円/m2 | 11万1845円/坪 | -0.74% |  |
| 40位 | 河南町 | 3万1250円/m2 | 10万3305円/坪 | -1.06% |  |
| 41位 | 岬町 | 2万3375円/m2 | 7万7272円/坪 | -3.58% |  |
| 42位 | 千早赤阪村 | 2万2300円/m2 | 7万3719円/坪 | -2.19% |  |
| 43位 | 能勢町 | 1万8550円/m2 | 6万1322円/坪 | -1.60% |  |
2024年[令和6年]基準地価
2024年[令和6年]公示地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
広告
マークをクリックすると市町村地価を表示
広告
大阪府の最新公示地価は平均34万3228円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では平均113万4639円/坪で、全国順位は2位/47都道府県です。前年からの変動率は+2.71%で、変動率の順位は10位/47都道府県です。
最新基準地価は平均40万6390円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では平均134万3440円/坪で、全国順位は2位/47都道府県です。前年からの変動率は+3.47%で、変動率の順位は6位/47都道府県です。
1983年(昭和58年)から42年分のデータがあり、公示地価の最高値は123万0668円/m2(1991年)、最安価格は20万1947円/m2(2005年)で、両者の違いは6.09倍です。基準地価の最高値は136万9986円/m2(1990年)、最低価格は19万8087円/m2(2005年)で、両者の違いは6.92倍です。
宅地の平均価格は15万5213円/m2、坪単位では51万3102円/坪、変動率は+2.73%です(2024年)。商業地の平均価格は110万0463円/m2、坪単価では363万7896円/坪、変動率は+9.41%です(2024年)。
大阪府の中で土地が高いのは、大阪市(107万6586円/m2)、吹田市(31万4560円/m2)、豊中市(25万3192円/m2)、茨木市(25万2904円/m2)、箕面市(24万3820円/m2)です。大阪府の中で土地が低いのは、能勢町(1万8550円/m2)、千早赤阪村(2万2300円/m2)、岬町(2万3375円/m2)、河南町(3万1250円/m2)、豊能町(3万3833円/m2)です。
バブル経済崩壊にともなう土地神話の崩壊とともに地価下落傾向が続いていた大阪府ですが、2006年[平成18年]より景気のゆるやかな回復に連動し、都心の商業地を中心に地価が上昇に転じました。しかし2008年[平成20年]に起きたリーマンショックの影響から翌年の公示地価より下落基調に転じました。アベノミクスによる景気回復により2013年[平成25年]より再び上昇基調に転じています。大阪市は梅田地区の再開発が続いており、同地区では地価上昇率が年20%を超える土地もでてきています。政令指定都市の堺市は市全体ではゆるやかな地価上昇傾向ですが、人口流出がつづく南区や生活利便性におとる美原区は地価下落傾向です。
2020年[令和2年]まで、大阪市は景気回復傾向とインバウンド需要に支えられ、大幅な地価上昇傾向を続けていました。大阪駅(梅田駅)周辺の再開発事業が継続しており、2011年[平成23年]に大阪ターミナルビル(大丸梅田店)が増床、大阪ステーションシティ(JR大阪三越伊勢丹)が開業しました。2012年[平成24年]に新梅田阪急ビル(阪急百貨店うめだ本店)が建て替えられました。2013年[平成25年]にグランフロント大阪が開業しました。2021年には大阪神ビル(阪神百貨店梅田本店)が建て替えられる予定です。これらの再開発により梅田地区では全国トップクラスの力強い地価上昇が起きました。また、阿倍野地区では、あべのハルカスが2014年[平成26年]に全面開業しました。コロナ禍前まではインバウンド経済が好調であり、大阪府は訪日外国人観光客が訪れる都道府県の全国1位となりました。外国人に人気の道頓堀、大阪城、USJ、海遊館などを抱える大阪市の商業地の地価上昇に寄与しました。しかし2020年[令和2年]に新型コロナウイルス禍が発生したため、観光業は試練のときをむかえています。
大阪市の中心部では2005年[平成17年]から2011年[平成23年]にかけて大型商業施設の新設や増床があいつぎ、商業施設の供給過剰が危惧され「大阪2011年問題」と呼ばれました。そごう心斎橋本店が建て替えを行って2005年[平成17年]に再オープンしました。2006年[平成18年]、南街会館になんばマルイが出店しました。2008年[平成20年]、近鉄百貨店阿倍野本店新館「あべのand」が「あべのHoop」の南隣に開業しました。2009年[平成21年]、そごう心斎橋本店が大丸心斎橋店 北館としてリニューアルオープンしました。2011年[平成23年]、高島屋大阪店と大丸梅田店(大阪ターミナルビル)が増床しました。同年、JR大阪三越伊勢丹(大阪ステーションシティ)が開業しました。その後も2012年[平成24年]に阪急百貨店うめだ本店(新梅田阪急ビル)が建て替えをし、2014年[平成26年]に「あべのハルカス」が全面開業するなど、大阪の商業の競争は熾烈さを増す一方です。しかしながら懸念されていた供給過剰問題は起きませんでした。おりしも外国人観光客数が急伸し、これらの商業施設がインバウンド需要の受け皿となりました。それぞれの商業施設は売り場を工夫し、ブラッシュアップし、競合他社との差別化をはかることによって、しのぎを削りながらも共栄することに成功したのです。
2011年[平成23年]、大阪ステーションシティがグランドオープンしました。大阪ステーションシティはJR大阪駅と周囲の再開発ビルがなる複合施設です。総延床面積は約53万m2に達します。大阪ターミナルビル株式会社により運営されています。大阪駅のほかには駅北側のノースゲートビルディング、駅南側のサウスゲートビルディングの2棟が存在します。ノースゲートビルディングにはルクア1100(JR大阪三越伊勢丹より改装)、ラグナヴェールPREMIER(結婚式場)、コナミスポーツクラブ、大阪ステーションシティシネマ、バルチカ(飲食店ゾーン)、ルクアフードホール、ルクアダイニングが入っており、地上14階~27階はオフィスです。サウスゲートビルディングは大丸梅田店、大丸エキウエダイニング美食区、ホテルグランヴィア大阪、総合クリニック、うまいものプラザからなります。
2019年[令和元年]まで大阪への外国人観光客数が増え続けていました。2018年[平成30年]は約1160万~1200万人に達しました。2009年[平成21年]から2016年[平成28年]にかけての外国人観光客数の増加率は世界一の約4.5倍で、年24%の伸び率となっています(米マスターカード社による統計発表)。円安傾向により日本全体への外国人観光客数が増えていますが、そのうちの約39%もの人々が大阪府を訪問しています(観光庁による訪日外国人消費動向調査)。主要空港である関西国際空港が存在することも理由のひとつですが、魅力的な観光地が多く、それらが近い距離に密集していることが大きな理由であると考えられます。特に人気があるのは道頓堀~心斎橋(大阪市中央区道頓堀、西心斎橋、心斎橋筋)、日本橋[にっぽんばし](大阪市中央区日本橋、大阪市浪速区日本橋)のある難波地区で、ショッピングや食文化に需要があります。また、大阪城(大阪市中央区大阪城)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪市此花区桜島)、海遊館(大阪市港区海岸通)、通天閣(大阪市浪速区恵美須東)、梅田スカイビル(大阪市北区梅田)も訴求力のある観光スポットです。しかし、2020年[令和2年]に新型コロナウイルス禍が発生したため、インバウンド経済は大きな打撃を受けています。
大阪府と大阪市は2013年[平成25年]に大阪観光局を設立しました。大阪観光局は松井一郎大阪府知事と橋下徹大阪市長(当時)が中心となり、大阪都市魅力創造戦略に基づいて発足させた公益財団法人です。当時日本を訪れる外国人観光客が増加していたのに対して大阪への観光約数の伸びはいまいちであったため、その危機感により発足。官民一体で大阪府、大阪市、関西経済界が出資しています。初代局長は加納国雄氏、2代目局長は溝畑宏氏です。ファッションモデルを大阪観光大使に起用して海外で広告展開をしたり、大阪国際音楽フェスティバルを開催して大阪の知名度向上をめざしました。関西国際空港へのLCC(格安航空会社)の就航を誘致し、LCCの便数は日本最多となりました。同空港は京都観光の玄関口にもなっており、京都へ近いことも大阪の強みとして生かしています。大阪市交通局は市営地下鉄にクラウド型ビデオ通訳サービスを導入し、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で観光客がコミュニケーションをとれるようにしています。大阪府や阪急電鉄などは無料Wi-Fiに力を入れ、観光情報のみならず医療情報や防災情報も複数言語で提供しています。大阪観光局は現在、スポーツ文化ツーリズムやカジノ統合型リゾートのプロジェクトを進行し、大阪を世界最高水準の観光都市にすることを志しています。
大阪万博が2025年[令和7年]4月13日~10月13日に大阪府大阪市此花区の夢洲で開催予定となっています。正式名称は「2025年日本国際博覧会」であり、公式略称は「大阪・関西万博」ですが、一般的に「大阪万博」と呼ばれています。大阪万博の構想は2014年[平成26年]に始まり、2018年[平成30年]にフランスで行われた第164回BIE総会での投票により、大阪が2025年国際博覧会の開催地に決定しました。日本における国際博覧会の開催は2005年[平成17年]の「愛・地球博」(愛知県)以来20年ぶりの6回目となります。大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、サブテーマは「Saving Lives(いのちを救う)、Empowering Lives(いのちに力を与える)、Connecting Lives(いのちをつなぐ)」です。コンセプトは「-People’s Living Lab- 未来社会の実験場」です。公式キャラクターの「ミャクミャク」は奇抜なデザインであり、大きな反響を呼びました。大阪万博のアンバサダーとしてコブクロ、佐渡裕、ダウンタウン、宝塚歌劇団、十代目松本幸四郎、山中伸弥が就任しました。大阪万博の準備が進められていますが、大きな問題が発生しています。“万博の華”とも呼ばれる海外パビリオンの建設が難航しているのです。建設遅れの背景には、建築資材の高騰、建設業の人手不足などがあります。円安やロシア・ウクライナ戦争により建築資材が高騰しています。労働人口の減少により建設業界においても人手不足が起こっています。また、2024年[令和6年]に建設業界において長時間労働の上限に規制がかかる、いわゆる「2024年問題」も工期に悪影響を与えることが予想されます。新型コロナウイルス禍が工期スケジュールの遅れに与えた影響もあります。大阪万博は課題が山積している状況です。
大阪府でお持ちの不動産の売却価格の査定をすることができます。
公示地価・基準地価の総平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 23万0248円/m2 | 76万1153円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 24万6181円/m2 | 81万3823円/坪 | +3.61% |  |
| 1985年[昭和60年] | 26万8406円/m2 | 88万7292円/坪 | +3.74% |  |
| 1986年[昭和61年] | 33万5732円/m2 | 110万9858円/坪 | +4.50% |  |
| 1987年[昭和62年] | 46万2231円/m2 | 152万8039円/坪 | +7.88% |  |
| 1988年[昭和63年] | 66万9236円/m2 | 221万2351円/坪 | +25.83% |  |
| 1989年[平成元年] | 91万4570円/m2 | 302万3374円/坪 | +35.59% |  |
| 1990年[平成2年] | 125万1717円/m2 | 413万7908円/坪 | +50.33% |  |
| 1991年[平成3年] | 123万5131円/m2 | 408万3080円/坪 | -6.16% |  |
| 1992年[平成4年] | 98万8134円/m2 | 326万6559円/坪 | -22.88% |  |
| 1993年[平成5年] | 73万3124円/m2 | 242万3551円/坪 | -15.46% |  |
| 1994年[平成6年] | 59万6385円/m2 | 197万1523円/坪 | -8.00% |  |
| 1995年[平成7年] | 48万4045円/m2 | 160万0151円/坪 | -5.45% |  |
| 1996年[平成8年] | 41万8194円/m2 | 138万2459円/坪 | -6.75% |  |
| 1997年[平成9年] | 38万6595円/m2 | 127万8002円/坪 | -3.83% |  |
| 1998年[平成10年] | 36万4194円/m2 | 120万3947円/坪 | -3.43% |  |
| 1999年[平成11年] | 33万3663円/m2 | 110万3018円/坪 | -7.19% |  |
| 2000年[平成12年] | 29万7038円/m2 | 98万1945円/坪 | -8.07% |  |
| 2001年[平成13年] | 26万7138円/m2 | 88万3103円/坪 | -8.45% |  |
| 2002年[平成14年] | 24万1931円/m2 | 79万9775円/坪 | -9.07% |  |
| 2003年[平成15年] | 22万3829円/m2 | 73万9932円/坪 | -9.04% |  |
| 2004年[平成16年] | 20万8052円/m2 | 68万7775円/坪 | -7.84% |  |
| 2005年[平成17年] | 20万0753円/m2 | 66万3646円/坪 | -5.07% |  |
| 2006年[平成18年] | 20万6032円/m2 | 68万1098円/坪 | -0.84% |  |
| 2007年[平成19年] | 22万8079円/m2 | 75万3981円/坪 | +3.62% |  |
| 2008年[平成20年] | 24万7245円/m2 | 81万7340円/坪 | +3.04% |  |
| 2009年[平成21年] | 23万4129円/m2 | 77万3983円/坪 | -3.24% |  |
| 2010年[平成22年] | 21万3566円/m2 | 70万6005円/坪 | -5.20% |  |
| 2011年[平成23年] | 20万8609円/m2 | 68万9619円/坪 | -2.85% |  |
| 2012年[平成24年] | 20万4915円/m2 | 67万7407円/坪 | -1.57% |  |
| 2013年[平成25年] | 21万2463円/m2 | 70万2357円/坪 | -0.67% |  |
| 2014年[平成26年] | 23万0634円/m2 | 76万2427円/坪 | +0.34% |  |
| 2015年[平成27年] | 23万9048円/m2 | 79万0244円/坪 | +0.53% |  |
| 2016年[平成28年] | 25万1873円/m2 | 83万2640円/坪 | +1.01% |  |
| 2017年[平成29年] | 26万7304円/m2 | 88万3650円/坪 | +1.11% |  |
| 2018年[平成30年] | 28万4552円/m2 | 94万0667円/坪 | +1.24% |  |
| 2019年[令和元年] | 31万5860円/m2 | 104万4165円/坪 | +1.84% |  |
| 2020年[令和2年] | 34万5373円/m2 | 114万1729円/坪 | +1.55% |  |
| 2021年[令和3年] | 32万7878円/m2 | 108万3895円/坪 | -0.65% |  |
| 2022年[令和4年] | 32万4841円/m2 | 107万3856円/坪 | +0.34% |  |
| 2023年[令和5年] | 33万4889円/m2 | 110万7073円/坪 | +1.51% |  |
| 2024年[令和6年] | 36万1312円/m2 | 119万4421円/坪 | +2.93% |  |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 22万4844円/m2 | 74万3286円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 24万0335円/m2 | 79万4498円/坪 | +3.62% |  |
| 1985年[昭和60年] | 26万2112円/m2 | 86万6486円/坪 | +3.74% |  |
| 1986年[昭和61年] | 33万2586円/m2 | 109万9458円/坪 | +4.04% |  |
| 1987年[昭和62年] | 42万7742円/m2 | 141万4024円/坪 | +6.06% |  |
| 1988年[昭和63年] | 61万9257円/m2 | 204万7133円/坪 | +22.19% |  |
| 1989年[平成元年] | 82万3178円/m2 | 272万1251円/坪 | +34.94% |  |
| 1990年[平成2年] | 115万5855円/m2 | 382万1009円/坪 | +56.05% |  |
| 1991年[平成3年] | 123万0668円/m2 | 406万8326円/坪 | +2.49% |  |
| 1992年[平成4年] | 102万4513円/m2 | 338万6822円/坪 | -22.88% |  |
| 1993年[平成5年] | 73万9904円/m2 | 244万5964円/坪 | -17.03% |  |
| 1994年[平成6年] | 59万8613円/m2 | 197万8886円/坪 | -8.67% |  |
| 1995年[平成7年] | 48万3869円/m2 | 159万9568円/坪 | -4.86% |  |
| 1996年[平成8年] | 41万5354円/m2 | 137万3073円/坪 | -6.68% |  |
| 1997年[平成9年] | 38万2362円/m2 | 126万4009円/坪 | -4.03% |  |
| 1998年[平成10年] | 36万1366円/m2 | 119万4598円/坪 | -2.94% |  |
| 1999年[平成11年] | 33万5466円/m2 | 110万8979円/坪 | -6.90% |  |
| 2000年[平成12年] | 29万9419円/m2 | 98万9817円/坪 | -7.78% |  |
| 2001年[平成13年] | 26万9575円/m2 | 89万1157円/坪 | -8.19% |  |
| 2002年[平成14年] | 24万4154円/m2 | 80万7121円/坪 | -9.03% |  |
| 2003年[平成15年] | 22万7221円/m2 | 75万1146円/坪 | -8.95% |  |
| 2004年[平成16年] | 21万0718円/m2 | 69万6588円/坪 | -8.15% |  |
| 2005年[平成17年] | 20万1947円/m2 | 66万7596円/坪 | -5.53% |  |
| 2006年[平成18年] | 20万4798円/m2 | 67万7018円/坪 | -1.52% |  |
| 2007年[平成19年] | 22万6628円/m2 | 74万9184円/坪 | +3.35% |  |
| 2008年[平成20年] | 24万9533円/m2 | 82万4905円/坪 | +3.72% |  |
| 2009年[平成21年] | 24万0734円/m2 | 79万5817円/坪 | -2.25% |  |
| 2010年[平成22年] | 21万7504円/m2 | 71万9022円/坪 | -5.64% |  |
| 2011年[平成23年] | 20万9922円/m2 | 69万3957円/坪 | -3.09% |  |
| 2012年[平成24年] | 20万5240円/m2 | 67万8481円/坪 | -1.76% |  |
| 2013年[平成25年] | 21万3849円/m2 | 70万6939円/坪 | -0.91% |  |
| 2014年[平成26年] | 23万1821円/m2 | 76万6351円/坪 | +0.25% |  |
| 2015年[平成27年] | 23万7992円/m2 | 78万6751円/坪 | +0.38% |  |
| 2016年[平成28年] | 24万1844円/m2 | 79万9484円/坪 | +0.96% |  |
| 2017年[平成29年] | 25万6447円/m2 | 84万7759円/坪 | +1.05% |  |
| 2018年[平成30年] | 27万2556円/m2 | 90万1014円/坪 | +1.13% |  |
| 2019年[平成31年] | 29万8443円/m2 | 98万6590円/坪 | +1.60% |  |
| 2020年[令和2年] | 33万6458円/m2 | 111万2260円/坪 | +2.08% |  |
| 2021年[令和3年] | 31万7052円/m2 | 104万8106円/坪 | -0.77% |  |
| 2022年[令和4年] | 31万1722円/m2 | 103万0488円/坪 | +0.15% |  |
| 2023年[令和5年] | 31万8991円/m2 | 105万4516円/坪 | +1.26% |  |
| 2024年[令和6年] | 34万3228円/m2 | 113万4639円/坪 | +2.71% |  |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 23万7403円/m2 | 78万4804円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 25万4075円/m2 | 83万9917円/坪 | +3.59% |  |
| 1985年[昭和60年] | 27万6824円/m2 | 91万5123円/坪 | +3.74% |  |
| 1986年[昭和61年] | 33万9796円/m2 | 112万3293円/坪 | +5.11% |  |
| 1987年[昭和62年] | 50万6500円/m2 | 167万4382円/坪 | +10.19% |  |
| 1988年[昭和63年] | 72万9408円/m2 | 241万1268円/坪 | +30.57% |  |
| 1989年[平成元年] | 102万7324円/m2 | 339万6114円/坪 | +36.62% |  |
| 1990年[平成2年] | 136万9986円/m2 | 452万8879円/坪 | +41.39% |  |
| 1991年[平成3年] | 124万0578円/m2 | 410万1084円/坪 | -16.49% |  |
| 1992年[平成4年] | 94万3185円/m2 | 311万7969円/坪 | -22.89% |  |
| 1993年[平成5年] | 72万3316円/m2 | 239万1130円/坪 | -13.55% |  |
| 1994年[平成6年] | 59万2636円/m2 | 195万9129円/坪 | -7.03% |  |
| 1995年[平成7年] | 48万4382円/m2 | 160万1263円/坪 | -6.44% |  |
| 1996年[平成8年] | 42万3605円/m2 | 140万0347円/坪 | -6.90% |  |
| 1997年[平成9年] | 39万4662円/m2 | 130万4669円/坪 | -3.46% |  |
| 1998年[平成10年] | 36万9586円/m2 | 122万1773円/坪 | -4.37% |  |
| 1999年[平成11年] | 32万9938円/m2 | 109万0706円/坪 | -7.81% |  |
| 2000年[平成12年] | 29万2119円/m2 | 96万5685円/坪 | -8.68% |  |
| 2001年[平成13年] | 26万2106円/m2 | 86万6468円/坪 | -8.98% |  |
| 2002年[平成14年] | 23万7341円/m2 | 78万4599円/坪 | -9.16% |  |
| 2003年[平成15年] | 21万6336円/m2 | 71万5162円/坪 | -9.22% |  |
| 2004年[平成16年] | 20万2163円/m2 | 66万8309円/坪 | -7.16% |  |
| 2005年[平成17年] | 19万8087円/m2 | 65万4833円/坪 | -4.06% |  |
| 2006年[平成18年] | 20万8857円/m2 | 69万0439円/坪 | +0.72% |  |
| 2007年[平成19年] | 23万1408円/m2 | 76万4987円/坪 | +4.23% |  |
| 2008年[平成20年] | 24万2120円/m2 | 80万0399円/坪 | +1.51% |  |
| 2009年[平成21年] | 21万9950円/m2 | 72万7108円/坪 | -5.38% |  |
| 2010年[平成22年] | 20万5248円/m2 | 67万8506円/坪 | -4.30% |  |
| 2011年[平成23年] | 20万5763円/m2 | 68万0209円/坪 | -2.34% |  |
| 2012年[平成24年] | 20万4211円/m2 | 67万5078円/坪 | -1.15% |  |
| 2013年[平成25年] | 20万9391円/m2 | 69万2202円/坪 | -0.12% |  |
| 2014年[平成26年] | 22万8301円/m2 | 75万4716円/坪 | +0.52% |  |
| 2015年[平成27年] | 24万1188円/m2 | 79万7316円/坪 | +0.83% |  |
| 2016年[平成28年] | 27万6218円/m2 | 91万3120円/坪 | +1.11% |  |
| 2017年[平成29年] | 29万4368円/m2 | 97万3117円/坪 | +1.26% |  |
| 2018年[平成30年] | 31万4452円/m2 | 103万9512円/坪 | +1.53% |  |
| 2019年[令和元年] | 35万9274円/m2 | 118万7683円/坪 | +2.45% |  |
| 2020年[令和2年] | 36万7594円/m2 | 121万5186円/坪 | +0.24% |  |
| 2021年[令和3年] | 35万4865円/m2 | 117万3110円/坪 | -0.36% |  |
| 2022年[令和4年] | 35万7543円/m2 | 118万1960円/坪 | +0.80% |  |
| 2023年[令和5年] | 37万4520円/m2 | 123万8083円/坪 | +2.13% |  |
| 2024年[令和6年] | 40万6390円/m2 | 134万3440円/坪 | +3.47% |  |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
大阪府でご所有なさっている土地の売却価格を査定することができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。
広告