群馬県の不動産の売却価格査定
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
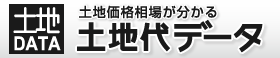
当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
| 順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎市 | 8万2320円/m2 | 27万2134円/坪 | +0.58% |  |
| 2位 | 前橋市 | 5万6462円/m2 | 18万6652円/坪 | +0.10% |  |
| 3位 | 太田市 | 4万1588円/m2 | 13万7480円/坪 | +0.70% |  |
| 4位 | 沼田市 | 4万0620円/m2 | 13万4280円/坪 | -0.78% |  |
| 5位 | 玉村町 | 3万5566円/m2 | 11万7575円/坪 | +0.00% |  |
| 6位 | 草津町 | 3万5466円/m2 | 11万7245円/坪 | +0.43% |  |
| 7位 | 伊勢崎市 | 3万4888円/m2 | 11万5334円/坪 | +0.00% |  |
| 8位 | 富岡市 | 3万4571円/m2 | 11万4285円/坪 | -1.24% |  |
| 9位 | 渋川市 | 3万4513円/m2 | 11万4093円/坪 | -0.80% |  |
| 10位 | 館林市 | 3万4377円/m2 | 11万3645円/坪 | -0.09% |  |
| 11位 | 吉岡町 | 3万4033円/m2 | 11万2506円/坪 | +0.28% |  |
| 12位 | 大泉町 | 3万1200円/m2 | 10万3140円/坪 | +0.00% |  |
| 13位 | 桐生市 | 2万8662円/m2 | 9万4752円/坪 | -1.07% |  |
| 14位 | みどり市 | 2万7650円/m2 | 9万1404円/坪 | -0.15% |  |
| 15位 | 藤岡市 | 2万6266円/m2 | 8万6831円/坪 | -0.98% |  |
| 16位 | 邑楽町 | 2万5500円/m2 | 8万4297円/坪 | -0.24% |  |
| 17位 | 中之条町 | 2万4733円/m2 | 8万1763円/坪 | -2.36% |  |
| 18位 | 明和町 | 2万4700円/m2 | 8万1652円/坪 | -0.20% |  |
| 19位 | 安中市 | 2万3387円/m2 | 7万7314円/坪 | -1.53% |  |
| 20位 | 榛東村 | 2万2400円/m2 | 7万4049円/坪 | -0.83% |  |
| 21位 | 甘楽町 | 2万0433円/m2 | 6万7548円/坪 | -0.85% |  |
| 22位 | みなかみ町 | 2万0300円/m2 | 6万7107円/坪 | -2.26% |  |
| 23位 | 下仁田町 | 1万8550円/m2 | 6万1322円/坪 | -3.14% |  |
| 24位 | 千代田町 | 1万8200円/m2 | 6万0165円/坪 | -0.22% |  |
| 25位 | 東吾妻町 | 1万8033円/m2 | 5万9614円/坪 | -0.74% |  |
| 26位 | 板倉町 | 1万5600円/m2 | 5万1570円/坪 | -1.48% |  |
| 27位 | 片品村 | 1万1333円/m2 | 3万7465円/坪 | -1.58% |  |
| 28位 | 昭和村 | 1万0800円/m2 | 3万5702円/坪 | -0.92% |  |
| 29位 | 長野原町 | 9326円/m2 | 3万0831円/坪 | -1.36% |  |
| 30位 | 川場村 | 9225円/m2 | 3万0495円/坪 | -0.78% |  |
| 31位 | 神流町 | 7470円/m2 | 2万4694円/坪 | -2.99% |  |
| 32位 | 高山村 | 7200円/m2 | 2万3801円/坪 | -1.37% |  |
| 33位 | 南牧村 | 4780円/m2 | 1万5801円/坪 | -2.85% |  |
| 34位 | 嬬恋村 | 3700円/m2 | 1万2231円/坪 | +0.00% |  |
| 35位 | 上野村 | 3280円/m2 | 1万0842円/坪 | -2.09% |  |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
マークをクリックすると市町村地価を表示
広告
群馬県の2025年[令和7年]の公示地価の平均は4万5490円/m2、坪単価では平均 15万0382円/坪で、前年からの変動率は-0.12%の下落です。公示地価の全国順位は34位/47都道府県です。公示地価の変動率の全国順位は38位/47都道府県です。
住宅地の最新の公示地価(2025年[令和7年])における群馬県の平均は3万7247円/m2、坪単価では平均 12万3131円/坪で、前年からの変動率は-0.25%の下落です。
商業地の最新の公示地価(2025年[令和7年])における群馬県の平均は6万6447円/m2、坪単価では平均 21万9660円/坪で、前年からの変動率は-0.05%の下落です。
工業地の最新の公示地価(2025年[令和7年])における群馬県の平均は2万3145円/m2、坪単価では平均 7万6513円/坪で、前年からの変動率は+2.34%の上昇です。
群馬県の市町村の公示地価平均は高い順に高崎市 8万2320円/m2、前橋市 5万6462円/m2、太田市 4万1588円/m2、沼田市 4万0620円/m2、玉村町 3万5566円/m2です。群馬県の市町村の公示地価の変動率は高い順に太田市 +0.70%、高崎市 +0.58%、草津町 +0.43%、吉岡町 +0.28%、前橋市 +0.10%です。
群馬県の公示地価は1983年[昭和58年]から43年分のデータがあり、公示地価の群馬県の平均の過去最高値は19万0619円/m2(1993年)、過去最低値は4万3880円/m2(2016年)で、二者の落差は4.34倍です。
群馬県の2024年[令和6年]の基準地価の平均は4万1894円/m2、坪単価では平均 13万8494円/坪で、前年からの変動率は-0.26%の下落です。基準地価の全国順位は25位/47都道府県です。基準地価の変動率の全国順位は31位/47都道府県です。
住宅地の2024年[令和6年]基準地価における群馬県の平均は3万1404円/m2、坪単価では平均 10万3815円/坪で、前年からの変動率は-0.53%の下落です。
商業地の2024年[令和6年]基準地価における群馬県の平均は7万2947円/m2、坪単価では平均 24万1150円/坪で、前年からの変動率は+0.18%の上昇です。
工業地の2024年[令和6年]基準地価における群馬県の平均は2万1528円/m2、坪単価では平均 7万1168円/坪で、前年からの変動率は+1.82%の上昇です。
群馬県の市町村の基準地価平均は高い順に高崎市 8万2811円/m2、草津町 6万7233円/m2、前橋市 5万4782円/m2、太田市 4万2976円/m2、吉岡町 3万7140円/m2です。群馬県の市町村の基準地価の変動率は高い順に草津町 +2.32%、太田市 +0.75%、高崎市 +0.60%、明和町 +0.35%、大泉町 +0.28%です。
群馬県の基準地価は1983年[昭和58年]から42年分のデータがあり、基準地価の群馬県の平均の過去最高値は13万4088円/m2(1992年)、過去最低値は3万7092円/m2(2017年)で、二者の落差は3.62倍です。
群馬県の地価の総平均(公示地価、基準地価の平均)は4万3573円/m2(2024年[令和6年])、坪単価では14万4045円/坪で、前年からの変動率は-0.35%の下落です。
群馬県の地価はバブル崩壊後の1993年[平成5年]より下落を続けています。群馬県の人口は減少傾向が続いています。アベノミクスによる日銀の低金利政策と、それに伴う円安傾向により製造業の多い群馬県の経済は景気回復傾向にあります。前橋市や高崎市の中心部で生活利便性の高いエリアの住宅地価は上昇または横這いとなっています。自動車産業を中心とした太田市の経済も堅調であり、駅周辺の住宅地価が上昇しています。群馬県の商業地価は高崎市、太田市の中心部が上昇を牽引しています。高崎駅・太田駅周辺の再開発事業が地価上昇に寄与しています。消費者の購買意欲はゆるやかに回復してきていますが、旧来からの商店街から大型商業施設に消費者が移行しており、商店街は衰退傾向が続いています。群馬県の工業地価は横這い傾向です。2018年[平成30年]上期に民間企業により取得された工業用地の件数および面積は群馬県が全国1位となりました。
1982年[昭和57年]に高崎駅に上越新幹線が開業して以来、高崎駅周辺では再開発が続いています。市街地再開発事業・優良建築物等整備事業により、高崎駅東口第一地区に高崎イーストセンタービル、第二地区に高崎イーストタワー、第三地区にツインシティ、第四地区に群馬トヨタビルおよびイーストパーク、第六地区にソルテ高崎イーストおよびパーク525、第八地区にホテル ココ・グラン高崎、第九地区にブリリアタワー高崎アルファレジデンシア、栄町に高崎タワー21が建設されました。高崎駅西口第一地区にウエストワンビル、第二地区にラ・メルセ、第五地区に井上山種ビル、旭町に旭町ビルおよびステイシア高崎が建設されました。高崎城跡の周辺にはシンフォニア高崎城址、国立病院機構高崎総合医療センター、高崎市総合保健センターが建設されました。2017年[平成29年]、ヤマダ電機本社のある「LABI1高崎」が「LABI1 LIFE SELECT高崎」としてリニューアルオープンしました(高崎市栄町)。栄町には高崎芸術劇場が2019年[令和元年]にオープンしました。高崎競馬場跡地には大型コンベンション施設「Gメッセ群馬」が2020年[令和2年]に開業しました。
群馬県でお持ちの不動産の売却価格の査定をすることができます。
公示地価・基準地価の総平均
不動産取引価格(土地のみ)の平均
1983年[昭和58年]~
広告
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 6万0767円/m2 | 20万0883円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 6万2535円/m2 | 20万6730円/坪 | +2.74% |  |
| 1985年[昭和60年] | 6万5095円/m2 | 21万5190円/坪 | +1.79% |  |
| 1986年[昭和61年] | 6万6770円/m2 | 22万0727円/坪 | +1.52% |  |
| 1987年[昭和62年] | 6万8002円/m2 | 22万4800円/坪 | +1.78% |  |
| 1988年[昭和63年] | 7万3223円/m2 | 24万2061円/坪 | +4.25% |  |
| 1989年[平成元年] | 9万7939円/m2 | 32万3768円/坪 | +11.17% |  |
| 1990年[平成2年] | 12万3062円/m2 | 40万6819円/坪 | +22.41% |  |
| 1991年[平成3年] | 14万7042円/m2 | 48万6090円/坪 | +18.28% |  |
| 1992年[平成4年] | 15万2510円/m2 | 50万4166円/坪 | +2.74% |  |
| 1993年[平成5年] | 13万8919円/m2 | 45万9239円/坪 | -3.56% |  |
| 1994年[平成6年] | 12万8995円/m2 | 42万6431円/坪 | -2.56% |  |
| 1995年[平成7年] | 12万3610円/m2 | 40万8628円/坪 | -1.80% |  |
| 1996年[平成8年] | 11万4672円/m2 | 37万9082円/坪 | -2.68% |  |
| 1997年[平成9年] | 10万7650円/m2 | 35万5869円/坪 | -2.43% |  |
| 1998年[平成10年] | 9万9040円/m2 | 32万7406円/坪 | -2.92% |  |
| 1999年[平成11年] | 9万3322円/m2 | 30万8504円/坪 | -4.59% |  |
| 2000年[平成12年] | 8万4262円/m2 | 27万8552円/坪 | -6.41% |  |
| 2001年[平成13年] | 7万6282円/m2 | 25万2172円/坪 | -6.98% |  |
| 2002年[平成14年] | 6万9598円/m2 | 23万0079円/坪 | -6.74% |  |
| 2003年[平成15年] | 6万3609円/m2 | 21万0280円/坪 | -6.89% |  |
| 2004年[平成16年] | 5万8614円/m2 | 19万3766円/坪 | -6.20% |  |
| 2005年[平成17年] | 5万5129円/m2 | 18万2246円/坪 | -5.14% |  |
| 2006年[平成18年] | 5万2862円/m2 | 17万4752円/坪 | -3.61% |  |
| 2007年[平成19年] | 5万1419円/m2 | 16万9982円/坪 | -2.32% |  |
| 2008年[平成20年] | 5万0712円/m2 | 16万7643円/坪 | -1.39% |  |
| 2009年[平成21年] | 4万9405円/m2 | 16万3323円/坪 | -2.47% |  |
| 2010年[平成22年] | 4万7472円/m2 | 15万6933円/坪 | -3.76% |  |
| 2011年[平成23年] | 4万5060円/m2 | 14万8961円/坪 | -4.52% |  |
| 2012年[平成24年] | 4万3095円/m2 | 14万2464円/坪 | -4.46% |  |
| 2013年[平成25年] | 4万2084円/m2 | 13万9123円/坪 | -4.09% |  |
| 2014年[平成26年] | 4万1021円/m2 | 13万5608円/坪 | -2.59% |  |
| 2015年[平成27年] | 4万0615円/m2 | 13万4267円/坪 | -1.54% |  |
| 2016年[平成28年] | 4万0528円/m2 | 13万3979円/坪 | -0.99% |  |
| 2017年[平成29年] | 4万0595円/m2 | 13万4199円/坪 | -0.73% |  |
| 2018年[平成30年] | 4万0628円/m2 | 13万4308円/坪 | -0.64% |  |
| 2019年[令和元年] | 4万0743円/m2 | 13万4690円/坪 | -0.62% |  |
| 2020年[令和2年] | 4万2998円/m2 | 14万2143円/坪 | -0.74% |  |
| 2021年[令和3年] | 4万3489円/m2 | 14万3766円/坪 | -1.04% |  |
| 2022年[令和4年] | 4万3283円/m2 | 14万3085円/坪 | -0.91% |  |
| 2023年[令和5年] | 4万3269円/m2 | 14万3038円/坪 | -0.71% |  |
| 2024年[令和6年] | 4万3573円/m2 | 14万4045円/坪 | -0.35% |  |
| 年 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 7万7341円/m2 | 25万5675円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 7万9101円/m2 | 26万1492円/坪 | +3.06% |  |
| 1985年[昭和60年] | 8万0899円/m2 | 26万7436円/坪 | +1.89% |  |
| 1986年[昭和61年] | 8万2745円/m2 | 27万3539円/坪 | +1.60% |  |
| 1987年[昭和62年] | 8万3886円/m2 | 27万7310円/坪 | +1.73% |  |
| 1988年[昭和63年] | 8万7800円/m2 | 29万0248円/坪 | +3.30% |  |
| 1989年[平成元年] | 11万4678円/m2 | 37万9102円/坪 | +10.49% |  |
| 1990年[平成2年] | 13万9512円/m2 | 46万1198円/坪 | +21.75% |  |
| 1991年[平成3年] | 17万7566円/m2 | 58万6995円/坪 | +26.90% |  |
| 1992年[平成4年] | 18万7105円/m2 | 61万8529円/坪 | +5.01% |  |
| 1993年[平成5年] | 19万0619円/m2 | 63万0146円/坪 | -2.87% |  |
| 1994年[平成6年] | 15万8641円/m2 | 52万4434円/坪 | -3.47% |  |
| 1995年[平成7年] | 14万8391円/m2 | 49万0551円/坪 | -2.14% |  |
| 1996年[平成8年] | 13万6454円/m2 | 45万1088円/坪 | -3.09% |  |
| 1997年[平成9年] | 12万7139円/m2 | 42万0295円/坪 | -2.92% |  |
| 1998年[平成10年] | 11万5812円/m2 | 38万2851円/坪 | -3.36% |  |
| 1999年[平成11年] | 10万5232円/m2 | 34万7876円/坪 | -4.59% |  |
| 2000年[平成12年] | 9万5101円/m2 | 31万4383円/坪 | -6.65% |  |
| 2001年[平成13年] | 8万6001円/m2 | 28万4301円/坪 | -7.44% |  |
| 2002年[平成14年] | 7万8202円/m2 | 25万8519円/坪 | -7.36% |  |
| 2003年[平成15年] | 7万1302円/m2 | 23万5710円/坪 | -7.45% |  |
| 2004年[平成16年] | 6万5613円/m2 | 21万6903円/坪 | -6.79% |  |
| 2005年[平成17年] | 6万1274円/m2 | 20万2560円/坪 | -5.85% |  |
| 2006年[平成18年] | 5万8206円/m2 | 19万2419円/坪 | -4.08% |  |
| 2007年[平成19年] | 5万6288円/m2 | 18万6077円/坪 | -2.73% |  |
| 2008年[平成20年] | 5万5605円/m2 | 18万3819円/坪 | -1.53% |  |
| 2009年[平成21年] | 5万4493円/m2 | 18万0143円/坪 | -2.04% |  |
| 2010年[平成22年] | 5万2522円/m2 | 17万3627円/坪 | -3.65% |  |
| 2011年[平成23年] | 5万0053円/m2 | 16万5466円/坪 | -4.49% |  |
| 2012年[平成24年] | 4万7777円/m2 | 15万7940円/坪 | -4.61% |  |
| 2013年[平成25年] | 4万5858円/m2 | 15万1599円/坪 | -4.26% |  |
| 2014年[平成26年] | 4万4853円/m2 | 14万8276円/坪 | -2.92% |  |
| 2015年[平成27年] | 4万4287円/m2 | 14万6403円/坪 | -1.72% |  |
| 2016年[平成28年] | 4万3880円/m2 | 14万5059円/坪 | -1.05% |  |
| 2017年[平成29年] | 4万4026円/m2 | 14万5541円/坪 | -0.64% |  |
| 2018年[平成30年] | 4万4086円/m2 | 14万5741円/坪 | -0.52% |  |
| 2019年[平成31年] | 4万4264円/m2 | 14万6330円/坪 | -0.46% |  |
| 2020年[令和2年] | 4万4467円/m2 | 14万7000円/坪 | -0.41% |  |
| 2021年[令和3年] | 4万5310円/m2 | 14万9788円/坪 | -1.00% |  |
| 2022年[令和4年] | 4万5031円/m2 | 14万8864円/坪 | -0.90% |  |
| 2023年[令和5年] | 4万4968円/m2 | 14万8655円/坪 | -0.78% |  |
| 2024年[令和6年] | 4万5145円/m2 | 14万9242円/坪 | -0.44% |  |
| 2025年[令和7年] | 4万5490円/m2 | 15万0382円/坪 | -0.12% |  |
| 年 | 基準地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 5万1117円/m2 | 16万8982円/坪 | ||
| 1984年[昭和59年] | 5万2694円/m2 | 17万4195円/坪 | +2.54% |  |
| 1985年[昭和60年] | 5万5231円/m2 | 18万2583円/坪 | +1.72% |  |
| 1986年[昭和61年] | 5万7584円/m2 | 19万0360円/坪 | +1.48% |  |
| 1987年[昭和62年] | 5万9051円/m2 | 19万5212円/坪 | +1.81% |  |
| 1988年[昭和63年] | 6万5028円/m2 | 21万4969円/坪 | +4.77% |  |
| 1989年[平成元年] | 8万8591円/m2 | 29万2863円/坪 | +11.58% |  |
| 1990年[平成2年] | 11万3875円/m2 | 37万6448円/坪 | +22.81% |  |
| 1991年[平成3年] | 13万0788円/m2 | 43万2358円/坪 | +13.25% |  |
| 1992年[平成4年] | 13万4088円/m2 | 44万3268円/坪 | +1.50% |  |
| 1993年[平成5年] | 11万3930円/m2 | 37万6629円/坪 | -3.91% |  |
| 1994年[平成6年] | 10万8954円/m2 | 36万0180円/坪 | -2.14% |  |
| 1995年[平成7年] | 10万3732円/m2 | 34万2918円/坪 | -1.58% |  |
| 1996年[平成8年] | 9万7200円/m2 | 32万1325円/坪 | -2.34% |  |
| 1997年[平成9年] | 9万2012円/m2 | 30万4172円/坪 | -2.04% |  |
| 1998年[平成10年] | 8万5559円/m2 | 28万2841円/坪 | -2.57% |  |
| 1999年[平成11年] | 8万2101円/m2 | 27万1410円/坪 | -4.59% |  |
| 2000年[平成12年] | 7万3818円/m2 | 24万4026円/坪 | -6.19% |  |
| 2001年[平成13年] | 6万6917円/m2 | 22万1215円/坪 | -6.53% |  |
| 2002年[平成14年] | 6万1309円/m2 | 20万2675円/坪 | -6.14% |  |
| 2003年[平成15年] | 5万6197円/m2 | 18万5776円/坪 | -6.34% |  |
| 2004年[平成16年] | 5万1659円/m2 | 17万0774円/坪 | -5.62% |  |
| 2005年[平成17年] | 4万8751円/m2 | 16万1163円/坪 | -4.41% |  |
| 2006年[平成18年] | 4万7072円/m2 | 15万5610円/坪 | -3.10% |  |
| 2007年[平成19年] | 4万6113円/m2 | 15万2442円/坪 | -1.87% |  |
| 2008年[平成20年] | 4万5510円/m2 | 15万0446円/坪 | -1.24% |  |
| 2009年[平成21年] | 4万4119円/m2 | 14万5849円/坪 | -2.91% |  |
| 2010年[平成22年] | 4万2287円/m2 | 13万9794円/坪 | -3.88% |  |
| 2011年[平成23年] | 4万0262円/m2 | 13万3097円/坪 | -4.54% |  |
| 2012年[平成24年] | 3万8595円/m2 | 12万7589円/坪 | -4.31% |  |
| 2013年[平成25年] | 3万8193円/m2 | 12万6258円/坪 | -3.90% |  |
| 2014年[平成26年] | 3万7528円/m2 | 12万4061円/坪 | -2.28% |  |
| 2015年[平成27年] | 3万7269円/m2 | 12万3205円/坪 | -1.37% |  |
| 2016年[平成28年] | 3万7159円/m2 | 12万2842円/坪 | -0.94% |  |
| 2017年[平成29年] | 3万7092円/m2 | 12万2621円/坪 | -0.83% |  |
| 2018年[平成30年] | 3万7097円/m2 | 12万2636円/坪 | -0.77% |  |
| 2019年[令和元年] | 3万7149円/m2 | 12万2807円/坪 | -0.78% |  |
| 2020年[令和2年] | 4万1429円/m2 | 13万6956円/坪 | -1.12% |  |
| 2021年[令和3年] | 4万1543円/m2 | 13万7335円/坪 | -1.10% |  |
| 2022年[令和4年] | 4万1415円/m2 | 13万6911円/坪 | -0.93% |  |
| 2023年[令和5年] | 4万1454円/m2 | 13万7040円/坪 | -0.65% |  |
| 2024年[令和6年] | 4万1894円/m2 | 13万8494円/坪 | -0.26% |  |
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
群馬県でご所有なさっている土地の売却価格を査定することができます(土地以外の不動産も可能です)。当サイトと提携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による査定フォームです。